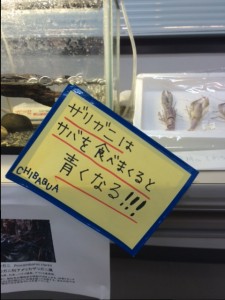ご覧いただきありがとうございます。
学習習慣スクールの鎌田です。
今回は振り返りの重要性についてお伝えします。
振り返りが重要と言われれば、なんとなくそうだなと思うのではないでしょうか。
振り返りをしないと、どうなるか?
では、振り返りをしないとどうなってしまうか考えてみましょう。
振り返りをしないと、一つひとつの経験がムダになってしまいます。
気がつかずに下記のような同じ間違いをくり返してしまう場合もあります。
・同じような問題でケアレスミスをしてしまう
・同じように問題文を読み間違えてしまう
また、表面的に振り返りをしても、あまり意味がありません。
・テスト勉強を始めるのが遅かったので、次はもっと早く始める
この振り返りは一見良さそうに思えますが
改善案が具体的でないことや何が原因で始めるのが遅かったのかなど
振り返りの深堀が不十分です。
この振り返りで次回のテスト勉強が早くから始められる子もいるかもしれませんが
多くの子はこれでは結局、テスト勉強を始めるのが同じくらいになり
そして同じ振り返りをすることになります。
振り返りがしっかりできる子の方が伸びる
振り返りをしっかりとおこなっても、すぐにテストの結果が良くなるとは限りません。
ただ次に活かせるような振り返りをしっかりとしている子は
後から必ず結果がついてきます。
そして、その経験が後になればなるほど増えていくので
結果も安定してきます。
テスト範囲や目標点は変わったとしても、テスト勉強のやり方は同じです。
定期テストでも模試でも受験でも、基本となる勉強のやり方は同じです。
高校受験だけではなく、大学受験、社会に出てからの試験でも同じです。
振り返りをしっかりとできるようにすると、こんな良いことがあります。
どのようなときに振り返りをするのか?
では、どのようなときに振り返りをすればいいのかお伝えします。
振り返りをするタイミングは大きく2つです。
1つ目は普段の勉強での振り返りです。
これは日々の勉強のなかで振り返りをしてください。
問題を解いて答え合わせをして、間違えてしまっていたら
なぜ間違えてしまったのかと考えてください。
問題ごとの振り返りなので、それほど時間はかからないはずです。
このすぐできる振り返りをするかどうかが成績を上げるうえでとても大事です。
2つ目は勉強全体の振り返りです。
例えば、定期テストの勉強についてなど。
テストが終わってから、各科目ごとの勉強や
勉強を始める時期、勉強のやり方などを振り返ります。
こちらは少し振り返りに時間がかかると思いますが
定期テストは年に数回しかないので、次回のテストのためにも
しっかりと振り返りをしましょう。
振り返りのやり方
次に、具体的な振り返りのやり方についてお伝えします。
結果 ⇒ 原因 ⇒ 対策
この順番で確認をしてください。
解いた問題が正解か不正解か、
テストの点数の結果が思っていたより良いか悪いか、
このような結果を確認することから振り返りは始まります。
思ったよりも結果が良くなければ、何が原因だったのかを考えます。
・テスト勉強が1週間しかできなかった
・ワークを1回しか解かなかった
原因については思いつく限り、できるだけ多く書き出してください。
原因のなかには大きなものもあれば小さなものもあるでしょう。
全てを書き出したうえで
どこから対策をしていくか優先順位を決めていけばいいのです。
書き出した原因に対して、一つずつ対策を考えていきます。
・テスト勉強を2週間前からやる
・ワークを少なくとも2回は解く
ここでもう少し踏み込んで考えていくことが重要です。
その対策をするためにはどうするか?
この点を意識してほしいと思います。
・テスト勉強を2週間前からやるにはどうすればいいか?
・ワークを少なくとも2回は解くにはどうすればいいか?
ここまでしっかりと考えましょう。
また原因と対策を考えるときは、具体的かどうかがポイントです。
あいまいなままでは実際に対策を実行できませんし、
次回に活かせる振り返りにならないこともあります。
ワークを1回しか解かなくて失敗したと感じたのなら
今度はワークを2回解こう、という対策になります。
そしてワークを2回解いてもあまり結果が変わらなければ
ワークを3回解こう、という新たな対策がでてきます。
振り返りの力をつけましょう
うまくいかなかったことの振り返りはもちろんですが
うまくいったことの振り返りもしましょう!
何のおかげ(原因)でうまくいったのか考えることで
自分に合ったうまくいく方法が見つかりやすくなります。
また、そこからさらに工夫をすることで
もっとうまくいく方法が見つかるかもしれません。
このように振り返りをすることで
うまくいかなかったことは改善して
うまくいったことはもっと改善することができます。
途中でも書きましたが、勉強のやり方は高校受験でも大学受験でも
社会に出てからの試験でも基本は同じです。
今、振り返りの力をつけておけばこれからずっと役に立ちます。
今のうちに勉強を通して、振り返りの力をつけてみませんか?


 v
v